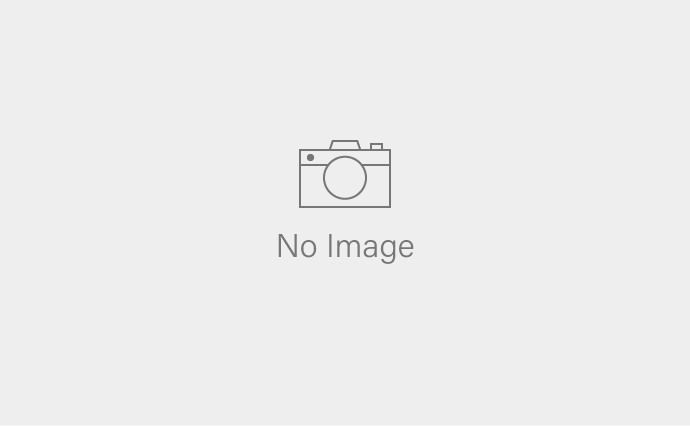みなさんご存じの、うさぎとカメの対決の話。うさぎが油断して寝ている間にカメが先にゴールします。
その話には続きがあります。
どうしても悔しいうさぎは、カメに再試合を申し込みます。いいですよと言うカメ。
そして再試合の日、絶対に負けられないうさぎは圧倒的な差でカメに勝利します。
そして、うさぎのゴールから随分遅れて、カメがゴールします。しかし、カメはなぜかニコニコしています。
負けたのに、どうしてそんなにニコニコしているのか、カメに聞いてみると、
カメは、「1回目より早くゴールできかたら、うれしい」と言うのです。
そんなカメの姿を目の当たりにし、ポカンと立ち尽くすうさぎでした。
先生「再試合でカメは負けたんです。でも、とてもニコニコしているのです。うさぎは気になって理由を聞くんだけど、カメはなんと答えたと思う?」など、
いろいろ交流しながら話を進めることができそうです。
一回目の勝負では、うさぎは勝利だけを目標に。
カメは完走することを目標に臨みました。
カメは最初からうさぎに勝つことなんてできないと思っていたでしょうし、生物の構造的にも、負けることは明らかです。
たまたまうさぎが寝ていたから勝負には勝ちましたが、勝とうが負けようがカメにとってはどうでもいいこと。
完走するという目標に向かって、カメは自分のできることを積み上げていきます。
もしカメが勝利にこだわっていたら、寝ているうさぎを追い抜くときに「あ、うさぎが寝ている!しめしめ、気づかれないように、そ~っと・・・」という描写があってもいいものですが、そんな描写はなかったように思います。
むしろ、道端に咲いている花を発見して喜ぶなど、新しい経験ができる機会を与えてくれたうさぎに感謝していたのかもしれません。
そして再試合でも、うさぎは勝負に執着し、カメはタイム更新を目標にし、レースに臨むのです。
最後の立ち尽くすうさぎは、何を思っているのでしょうか。
うさぎにとって、この経験が、彼の今後の人生に役立つことを願うばかりですね。
中学1年生の道徳の教科書に、「カメは自分を知っていた」という教材がありました。百人一首を覚えて優勝することだけを目標にしていたAさんに対して、百人一首のおもしろさを味わっていたBさん。最終的に百人一首大会で優勝したのはBさんでしたが、優勝というのはあくまで結果です。目標を自分で設定し、その過程を楽しめるかが大事だという内容に、私は受け取りました。
しかし、カメは自分を知っていたというタイトルのせいで、解釈に差が生じるかもしれません。
カメ「コツコツがんばることが自分の特技だから、続けていればいつかウサギに勝利できるのだ!」という、
変な根性論に発展する可能性もあります。
1回戦だけの話で、かつ幼い子に話すならそれでもいいでしょうが、学年が進むにつれて、解釈を深めるのがいいでしょう。
「カメは自分を知っていた」ではなく、「カメは最初から勝負など見ていなかった」の方が、個人的にはわかりやすいなと思います。
数字や他人との比較にこだわると、しんどいし、いつか目標を失うでしょう。そんな時にでも、「自分にできることはなんだろう」を問う、いい素材だと思います。